
-
お電話での問い合わせは03-6805-2586
- メールフォーム
お電話での問い合わせは03-6805-2586

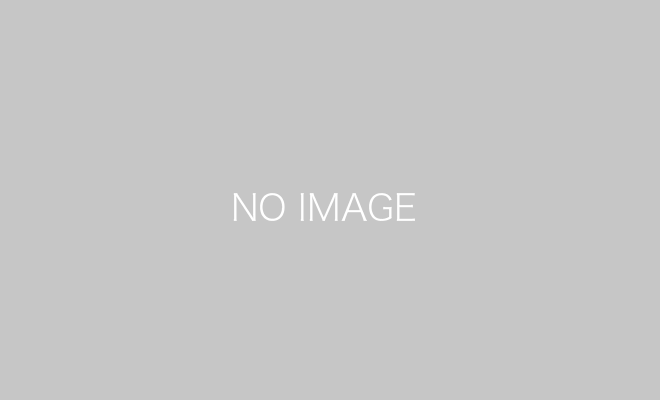
駒澤綜合法律事務所 所長 高橋郁夫が、2024年11月に開催された宇宙の未来での「宇宙リスクガバナンス」での話した内容が…

世界知的財産の日記念上映会-スーパーマリオブラザーズ・ムービーをみてきました。MPAさん、ご招待いただきありがとうござい…

IT 法部会・宇宙法部会でご一緒しております星諒佑先生より「ライブコマースの法律」の献本をいただきました。写真は…

グローバル・プライバシー・ノーティスというのが、どのようなもので、どのようなフレームワークで考えていくべきかというのを「…

国際的なサービスを提供する、特に、ウェブ上でのサービスを提供する企業にとっては、プライバシーポリシー保護/プライバシーノ…